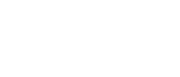お知らせ
【法情報】プラ新法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)について

廃棄物業界の動きとして、2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」についてご紹介いたします。 資源循環に関する法律ですが、事業者・廃棄物処理業者に限らず、私たち個人の日々の生活にも深く関わる法律です。この法律について解説します。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラ新法)の目的
・製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進
・プラスチックの資源循環を促進する必要性が高まっていること
プラ新法における個別の役割
設計・製造
・製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定
・指針に適合した製品であることを認定する仕組み
・認定製品を国が率先して調達(グリーン購入法上の配慮)
・リサイクル材の利用に当たっての設備への支援
販売・提供事業者
・ワンウェイプラスチックの有償化や提供の抑制
・代替素材への転換や再利用可能な製品の推奨
排出・回収・リサイクル段階
・市区町村の分別収集・再商品化
①プラスチック資源の分別回収を促す為に、容器包装リサイクル法に基づくルートの活用を認める
②市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画の策定
・製造・販売事業者等による自主回収
①自主回収再資源化する計画の策定と実施
②認定事業者には廃棄物処理法の許可が不要となる特例が適用される
・排出事業者の排出抑制・再資源化
①排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定
②排出事業者等が再資源化計画を作成
・特定プラスチック使用製品提供事業者について
①対象となるのは、飲食店や小売店で提供されるプラスチック製のフォークやスプーン、ホテルのアメニティ、衣類の包装カバーなどである
②一定量以上の特定プラスチック使用製品廃棄物を排出する事業者が、排出量削減の取り組みを著しく怠った場合、勧告・公表・命令などの措置が取られる
どのような変化が想定されるか
本法律の施行により、今まで一般廃棄物として処理され、自治体のクリーンセンターなどで焼却処理・サーマルリサイクルをされていたプラスチックを焦点にあてたマテリアルリサイクルルートの構築が可能となります。マテリアルリサイクルを行う際、最も重要なことは集荷時における荷の品質をどこまで一定に保つことができるかという部分ですが、製品単位の回収ルートの構築、行政回収に新たな一品目を加えることで、その課題を解決することが期待されています。
また、その制度構築にあたって、業の許認可の問題・設備投資(回収・処理インフラの構築)に関しても支援策や特例が認められることにより、仕組み構築の難易度を下げています。とはいえ、費用や制度的な部分だけではなく、今までの事業インフラの有無という参入障壁は未だ高く、既存の処理フローをどのように改善し、これを仕組化するかという部分が現状の認識といえます。
一方、脱炭素社会が進むにつれて、リサイクルループ・サーキュラーエコノミーに対する経済合理性(社会的責任の遂行と実利双方を踏まえた)も取れるようになっていくことが想定される中で、新たなリサイクルルート構築に関する事例が生まれてくる期待もあります。
まとめてみると
製造段階から提供・販売・処理という工程で各事業者に対する役割を明確にすることで、プラスチックの資源循環を促すことを目的としています。プラスチック資源とされていますが、対象となるのは主に一般廃棄物(家庭や事業所から排出される廃棄物)です。個人から排出する廃棄物の場合では、一部自治体ではごみ回収の区分のひとつに「プラスチックごみの日」が加えられるなどしているケースも見られます。
廃棄物に関する法律では、直近これ以外に「再資源化事業等高度化法」という法律が2024年5月に公布されており、いずれも、資源循環フローの全体的なレベルアップを目指すものであり、マテリアルリサイクルを促進するために、製造・提供・排出・処理に関わる各事業者・個人に対して役割を定義するものとなります。
今後の法規制などについてもピックアップし、皆様にお伝えができればと思います。
脱炭素社会の実現に向けて ~廃棄物処理を通じた貢献~

近年の異常気象や自然災害の増加は、地球温暖化の影響を私たちに強く意識させています。2024年11月に開催されたCOP29の直前、EUの気象機関から2024年の世界の平均気温が、産業革命前と比べて初めて「1.5℃」以上上昇する見通しという報告もあり、気候変動による深刻な影響を回避するため、世界の脱炭素化をさらに加速させる必要があることが改めて認識されました。
このような状況の中、当社は廃棄物処理事業者として、どのような貢献ができるのかを真剣に考え、お客様との対話を重視しながら、脱炭素化に向けた取り組みを進めてまいります。
廃棄物処理におけるGHG排出量への考察
廃棄物処理は、企業活動における温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告の枠組みである「スコープ3」のカテゴリー5に該当し、GHG排出量算定が求められる部分です。ここでは、廃棄物処理におけるGHG排出量に関する考え方について解説します。
環境省が公表している「排出原単位データベースVer.2.6」によると、廃棄物の処理においては、品目別にリサイクル・焼却・埋立のいずれが脱炭素に資するかは異なってきます。
例えば、以下の2品目を例に見てみましょう。
廃プラスチック類 1tあたりの処理について発生するGHG
焼却:2.6833t-CO2
埋立:0.0851t-CO2
リサイクル:0.1490t-CO2
紙くず 1tあたりの処理について発生するGHG
焼却:0.0837t-CO2
埋立:2.5127t-CO2
リサイクル:0.0210t-CO2
(リサイクルについては、特定の手法に定義されていることを留意)
このように、品目によって最適な処理方法は異なり、場合によっては「安価な処理=環境負荷が大きい」ということもあり得ます。
当社がご提供できること
廃棄物処理における脱炭素化で最も重要なのは、排出量を減らすこと(発生抑制)です。そして、次に重要なのは、GHG排出量の少ない処理方法を選択することです。当社では、お客様の脱炭素化を支援するため、以下のサービスを提供しています。
発生抑制のサポート
お客様と共に品目の分別を検討し、廃棄物として扱わずにリサイクルできるものを明確化します。必要に応じて、リサイクル方法の提案や導入支援も行います。
最適な処理方法の選定
価格、処理方法、GHG排出量などを考慮し、お客様にとって最適な処理方法を提案します。お客様の事業内容や廃棄物の種類、排出量などを把握した上で、最適な処理方法を検討します。
脱炭素に関して、日々刻々と取組みのスピードが速まっているように感じます。当社としても、情報を集めると同時に対話を通して、皆様の脱炭素活動に貢献していきたいと思っております。
廃棄物処理における脱炭素の考え方

脱炭素に取り組んでいく中で、一つのゴールの指標となるのがGHG(GHG※Green House Gas:温室効果ガス、CO2もこれに含まれる)の削減です。
上場企業の方々においては、気候変動リスクに対する対応という観点の一つに、気候変動を起こさないようにするというテーマがあり、その点においてもGHGの削減は重要なテーマといえます。また、国際的にもGHG削減に向けた各種イニシアチブ(認証のようなもの)が存在し、今後その重要性は高まる一方でしょう。
GHGの算出の方法
では、このGHGはどのように算出されるのでしょうか?
大きく3つの区分から算出することが求められています。
Scope1:自社が直接排出するGHG
燃料の燃焼や、製品の製造などを通じて企業・組織が「直接排出」するものをScope1とする
Scope2:自社が間接排出するGHG
他社から供給された電気・熱・蒸気を使うことで、間接的に排出されるGHG
Scope3:サプライチェーンで排出されるGHG
原材料の調達から社員の通勤・出張費、製品の使用に伴うCO2排出量まで事業にかかわる領域を計算対象とするのがScope3
次に、どのようにCO2の排出量を算出するかというと、これは大きく2つの方法があります。
一次データを用いる場合:自ら収集・把握したデータを用いて積み上げていく方法
二次データを用いる場合:物量や取引金額を活動量として定義し、それに排出原単位を掛けて算出する方法
理想論は一次データを用いて算出することです。しかし、情報を集めることは現実的に難しく、多くの事業者が二次データを用いて算出をしています。
廃棄物とGHG
さて、本題として廃棄物におけるGHGという点をお話していきたいと思います。
廃棄物の排出について、以下の部分でGHG排出を計算する必要があります。
Scope3 CATEGORY5「事業から出る廃棄物」
自社で発生した廃棄物の輸送処理に伴う排出
Scope3 CATEGORY12「販売した製品の廃棄」
使用者(消費者・事業者)による製品の廃棄時の処理に伴う排出
という2つがあります。
(ここまで算出対象になっているということをご認識ください)
CATEGORY5のほうについては、皆様自身で処理方法やリサイクルを検討することができますが、CATEGORY12については使用者の方々が決定されるので掴みづらい部分かと思います。
では、この廃棄物について、どのような原単位が設定されているか確認してみましょう。
環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース」
Ver.3.4(EXCEL)<2024年3月リリース>より
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html
焼却処理されるもの:0.0472(tCO2/t)+品目原単位
埋立処理されるもの:0.0472(tCO2/t)+品目原単位
リサイクルされるもの:
廃プラスチック類0.136(tCO2/t)・木くず0.008(tCO2/t)…と品目が続きます。
私たちができる脱炭素のご提案
私たちが、この皆様のGHG排出量削減に取り組めることは以下のことであると考えます。
・廃棄物の選別精度を徹底的にリサイクル比率を上げられるようにする
ある一定品質までは、リサイクル=コスト削減になります(焼却処理・埋立処理にするほうが処理単価が高い)。
現在は、皆様方にご提示できる価格を優先させていますが、GHG削減のためには更なる選別が必要になるでしょう。
・より低炭素処理ができる、二次処理先へ搬入する
処理方法において、より低炭素に処理ができる処分先を探すことです。皆様の廃棄物を我々が分別・一次処理をして、低炭素で処理できる処理場へ依頼することで、GHGの排出量は減らせます。
GHG削減について、ご相談がありましたら、まずはご連絡ください。