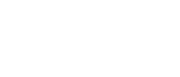お知らせ
エシカル粗大ごみ・不用品回収「エシッちゃるら」を期間限定提供

この度、弊社の粗大ごみ・不用品回収サービス「うっちゃるら」において、環境配慮型の不用品回収サービスとして「エシッちゃるら」という新ブランドを期間限定で創設することをご報告いたします。
脱炭素化が求められる世の中において、当社の廃棄物処理業・資源循環ビジネスは重要な役割を担っています。分別を行い、適正な処理ルートを選定することで、リサイクル率の向上を通して、地球環境に貢献をしてまいりました。一方で、処理機械の稼働に伴うエネルギーや運送時における燃料消費については、事業規模と比例する形で増えるものであり、この部分に対する改善については課題となっておりました。その中で創設するのが「エシッちゃるら」です。
「エシッちゃるら」とは?
「エシッちゃるら」は粗大ごみ・不用品回収サービス「うっちゃるら」に環境配慮の要素を加えた専門ブランドです。
通常の回収料金に、回収場所から処理場までの距離に応じた費用を追加でご負担いただくことで、粗大ごみ・不用品の回収時に発生するCO₂をオフセットできる取り組みです。
お預かりした費用は、J-クレジット制度を用いて森林由来のカーボンクレジット購入に充てられ、地域の森林保全活動へと還元されます。
さらに、「エシッちゃるら」をお申し込みいただいたお客様には、地球温暖化防止への貢献を証明するオリジナルノベルティを進呈いたします。
代表者コメント
「ごみを“ただ捨てる”から、“地球にやさしく片付ける”へ。」
エシッちゃるらを通じて、お客様が手軽に環境保全へ参加できる仕組みをつくりたいと考え、このサービスを開発しました。私たちはこれからも、地域密着・環境配慮・安心安全を柱に、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。
ぜひこの機会にエシッちゃるらをご利用ください。
エシッちゃるらのサービス紹介ページ
うっちゃるらHP内、エシッちゃるら専用ページ
https://www.uttyarura.com/ethiccyrura/カーボンオフセットリースを活用した塵芥車の導入

この度、ACP商事では静銀リース株式会社様の「カーボン・オフセットオートリース」を用いて塵芥車を導入いたしました。当社としては、オフセットされた車両を用いて廃棄物収集運搬を行うことになります。
昨今、気候変動・地球温暖化は進む一方で、各企業とも、それらに対する対応策が求められています。当社は、静銀リース株式会社による、本枠組みを活用することで、気候変動対策に寄与する車両を取得することとなりました。これに限らず、日々の業務品質の向上やエコ活動を通して、環境対策に貢献してまいります。
静銀リース株式会社「カーボン・オフセットオートリース」について
静銀リース株式会社様では、SDGsの達成に向け、事業活動を通じて持続可能な社会の実現をめざす企業を支援されています。その取り組みの一環が、J-クレジット(国が認証したCO2排出削減・吸収量)を活用した「カーボン・オフセットオートリース」です。
特徴
・乗用車、商用車、二輪車など、車種制限はなし
・リースバック契約も対象
※ACP商事では塵芥車を導入
カーボン・オフセットの流れ
①当社が使用するリース車両の車種ならびに走行予定距離に基づきCO2排出量を静銀リースが算出
②静銀リースが J-クレジットを購入し、算出した CO2 排出分を無効化
当社において
当社においては、静銀リース株式会社において、オフセットされている塵芥車を導入したことになります。当社においては、様々な選択肢がある中で、本スキームによる車両を導入したことは、当社における気候変動対策に対する考え方を表すものです。
当社代表 小笠原より
当社の事業は、資源循環の一翼を担うものであり、気候変動対策においても重要な役割を担っていると自負しております。リサイクル率の向上といった事業品質の追求はもちろんのこと、事業に用いる車両や設備の選定においても環境配慮を徹底することで、地球環境に貢献できるものと考えております。
今回は当社の車両の更新時期と静銀リース株式会社様のご提案が相まって、カーボンオフセットリースという形で環境問題に対して取り組むこととなりました。これからもあらゆる可能性を検討し、気候変動対策に取り組んでまいりたいと考えています。
【廃棄物動向】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律

令和7年2月1日より施行された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下、高度化法)」をご紹介します。
この法律は廃棄物処理業界だけでなく、製造業に従事されている皆様にとっても大きな意味を持つものです。資源循環の新たな流れを構築することを目的としており、製造工程における原材料調達においてリサイクル品の活用が進むことが期待されています。
高度化法の背景:脱炭素社会への転換
高度化法の根底には、脱炭素社会への移行という大きな流れがあります。国の試算によれば、廃棄物処理業自体の温室効果ガス(GHG)排出量は全体の3.2%にとどまりますが、処理工程から生まれる再生資源を活用することで、国内全体のGHG排出量の約36%を削減できる可能性があるとされています。
つまり、バージン材に代わってリサイクル資源を利用することは、地球温暖化対策への大きな一歩となるのです。このような背景から、高度化法では、効率的かつ高品質な再生資源原料の製造に焦点が当てられています。
さらに現在、「静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」において、法律の具体的な運用ルールも議論されています。製造業者がリサイクル原料を選びやすくする仕組みの構築が目指されています。
廃棄物処理業者への主な施策
高度化法では、主に以下の3つの取り組みが廃棄物処理業者に求められています。
事業形態の高度化
製造業側が求める質・量の再生資源を安定的に確保するため、広域的な分別収集・再資源化事業の推進が求められます。この計画が環境大臣に認められると、廃棄物処理業者に対して業許可の特例が認められます。製造業者としては、処理業者と連携することで安定的な資源供給体制を築くことが可能です。
高度分離・回収事業の推進
特に分別が難しい廃棄物(例:太陽光パネル)について、有用な部分を分離・回収する取り組みが評価され、認定されることで特例措置の対象となります。
再資源化工程の高度化
再資源化工程の効率化や温室効果ガス排出量の削減に寄与する設備導入計画が認められた場合、業許可の変更において緩和措置が適用されます。
製造業者に求められる対応
高度化法では、製造業者にも以下のような取り組みが求められています。
・廃棄物を分別して排出し、その再資源化を進めること。
・製品設計段階から、廃棄後に有用部分を分離しやすくする工夫を行うこと。
・再生資源や再生部品を積極的に活用し、資源循環型のものづくりを推進すること。
これらの対応は単なる法令順守にとどまらず、今後のエシカル消費の広がりや、カーボンプライシングの導入など、社会的・経済的な変化にも対応する重要な視点となります。価格や品質面での課題もありますが、長期的には再生資源の価値が高まっていく可能性があるでしょう。
ACPグループとしての支援
高度化法の施行を受け、今後さまざまな動きが本格化していくと予想されます。この法律の目的は、より高度な資源循環の実現です。再生資源を活用した製品が選ばれる時代が近づいています。
製造業に携わる皆様にとっても、今後の製品設計や原材料選定の在り方を見直すきっかけとなるかもしれません。 ACPグループでは、幅広いネットワークを活用し、皆様の再資源化に関する課題解決をサポートいたします。 より詳しいご相談をご希望の際は、どうぞお気軽にお声がけください。